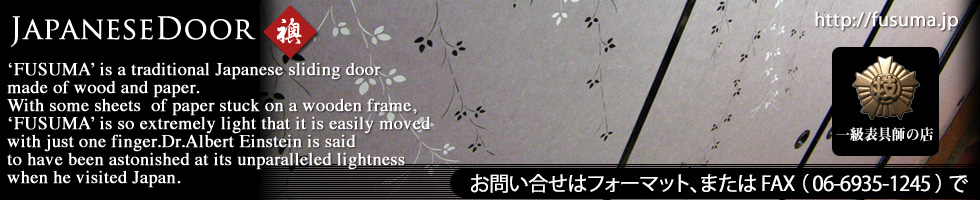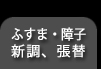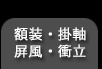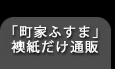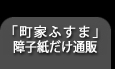「襖はすぐに破れる」と言われます。しかし、そういわれる襖は、近代作成されるようになった「簡易襖」です。昔ながらに作られる本襖(ふすま)は、何重にも和紙を重ねて作成されており、自然調湿をし、和紙の風合いを醸し出します。 当店ではお客様よりご希望があれば、今も昔ながらに作られる本襖(ふすま)を、作成しております。
「襖といえば桂離宮」と言われる方が多いかと思います。藍染め・紺色の和紙と未晒しの白い市松の襖。当然のことながら、あの桂離宮の襖は「本襖」です。手漉き和紙を使用し、紙は張替の際に、漉き返し(貼られている和紙を再度染色して、もう一度紙漉をする)をすると耳にしたことがあります。「和紙」と「本襖の骨」で作成された襖は、「数百年使用可能」と言うことも証明済みです。
 骨地となる襖骨には、金物などは一切使用せず「竹釘」で組まれており、襖骨を開口に合わせて削り、手漉楮和紙などの繊維の強い和紙を張って、襖骨(組子骨)を締め付けてガタつきなどがないようにします。(骨縛り)
骨地となる襖骨には、金物などは一切使用せず「竹釘」で組まれており、襖骨を開口に合わせて削り、手漉楮和紙などの繊維の強い和紙を張って、襖骨(組子骨)を締め付けてガタつきなどがないようにします。(骨縛り)
襖骨(組子骨)が表面から透けないように、また「骨縛り」をより強固にするために厚手の紙を張ります。(胴張り)その上から、薄い手漉楮和紙や大福帳など100年以上経過した楮和紙をロール状にして、その和紙をずらしながら重ねて蓑虫の巣のように張ってゆきます。(蓑貼り)
 この下貼り(蓑貼り)に使われる薄い楮和紙(大福帳や手紙など)を「反古紙」といいます。古い楮和紙は、和紙特有の伸縮が少なく、また「墨」には「防虫効果」があるため、このような「反古紙」を使って下貼りがされます。(リサイクルの意味も含まれていたモノと思われます。)小説や歴史上の発見などで「襖から、Aさんの手紙がでてきた!」とあるのは、「反古紙」としてその手紙が使用されたからです。
この下貼り(蓑貼り)に使われる薄い楮和紙(大福帳や手紙など)を「反古紙」といいます。古い楮和紙は、和紙特有の伸縮が少なく、また「墨」には「防虫効果」があるため、このような「反古紙」を使って下貼りがされます。(リサイクルの意味も含まれていたモノと思われます。)小説や歴史上の発見などで「襖から、Aさんの手紙がでてきた!」とあるのは、「反古紙」としてその手紙が使用されたからです。
 蓑張りの紙を固定させるため、上から楮和紙を張ります。(蓑押さえ)
蓑張りの紙を固定させるため、上から楮和紙を張ります。(蓑押さえ)
簑押さえが終わった時点で、実際にはめ込む現場へ持ち込み、微調整を行い(地合わせ)、持ち帰って襖骨に張られた和紙の段差を均一にするため、段になった和紙の部分を出刃包丁でこそいでゆきます。
その後、薄手の手漉楮和紙を用い、紙の切り口を喰い裂きにして袋状に薄い和紙を張り付けます。(浮け張り)この浮け張りは、上張り紙が下地に直接付くのを防ぎます。この上から「上張り紙」を補強するために、和紙を張ります。(清張り)最後に、表面に見える「上張り紙(ふすま紙)」を張り込みます。
*採寸から作成に約1ヶ月お時間を頂戴いたします。
詳細はお問い合せ下さい。